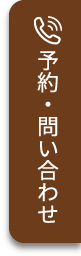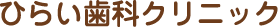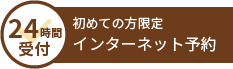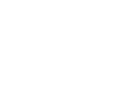お歯黒について
現代においては白い歯が美しさの象徴ではありますが、昔はこれとは逆に歯を黒くしていたことをご存知ですか?今回は、お歯黒についてご紹介します。
お歯黒とは
女性や一定の身分にある人が歯を黒く染める風習を「お歯黒」といいます。日本古来のものである、という説や外国から伝わったという説様々あるようです。いつから始まったのかということの詳細は明らかになっていませんが、明治初期頃まで1200年以上長く続いたものといわれています。江戸時代においては既婚している女性の象徴であったという説もあります。この時代には、女性がお歯黒を施す様子などが浮世絵として描かれていました。のちには、天皇や公卿など一定の身分にある男性もお歯黒をするようになったようです。明治政府の近代化政策によりお歯黒禁止令が出されたことで、その習慣は徐々に姿を消しました。
お歯黒は何でできている?
お歯黒の主成分は酢酸に鉄を溶かした液体を使用していたといわれています。鉄漿(かね)水とも呼ばれたその液体を歯に塗り、五倍子粉(ふしこ)というタンニンを多く含む粉を塗ります。酢酸とタンニンの化学反応によりタンニン酸第二鉄が生成され、黒くなる仕組みです。
お歯黒でむし歯予防?
お歯黒が長く続いたの歯、むし歯になりにくい、むし歯の進行を抑制するといった効果があったからではないかと言われています。タンニンは歯や歯ぐきのタンパク質を凝固させて細菌の侵襲を抑制する効果があるほか、鉄漿水に含まれる第一鉄イオンはエナメル質の主体であるハイドロキシアパタイトを強化して酸から守る効果があります。また、空気に触れることによる酸化で生成された第二鉄イオンは、タンニンと結合すると膜を形成し、その膜が歯の表面を覆うことで細菌から保護する働きがあります。このように、お歯黒により歯の無機質、有機質の両面から歯質を強化してむし歯を予防する効果を得ていたようです。
まとめ
歯を黒く染めるということは現在の私たちからすると想像もつかないことですが、お歯黒は日本人にとって様々な意味や働きをもつ習慣であったようです。時代によって美しさの概念は様々ですが、むし歯を予防して歯の健康を守りたいという意識は同じではないでしょうか。
むし歯や歯周病を予防することは、自分の歯で美味しく食事を楽しむためにもとても大切なことです。定期健診のご予約やお口の中のことでお悩みのことがございましたら、お気軽にご相談ください。